
Related Articles

モリンガに正面から向き合い研究をされているという東京理科大学薬学部の板倉先生。確かに栄養価の高いモリンガではあるけれど、「薬」という分野で何を研究されているのか?
日々、我々もお世話になることの多い薬において、モリンガにも大いなる可能性が秘められているなんて、想像もしていなかったこと。ただのスーパーフードじゃないのかも・・・今回は先生も研究に励んでいる東京理科大学の葛飾キャンパスにお邪魔して、まずは専門分野についてのお話から始まります。(研究員MIKI)

専門は薬学部の中でも「薬剤学」です。薬剤学は、薬そのものではなく、「どうすれば薬が体の中で一番良く働くか」を考える学問なんです。「薬」というと、例えば頭痛薬ならアセトアミノフェンなどが有効成分になりますが、それを1日何回、どのような量で飲めば効くのか、その成分の効き目を長くするにはどうすれば良いか、などを考えて製剤設計や評価を行います。これは、有効成分である化合物を、いかに体の中の目的の部位に届け、より効果的に作用させるために、「体内で薬の動きをどうコントロールするか」を追求する分野なのです。
ナノ粒子って聞いたことありますか?ナノ粒子は、目に見えないくらいの小さな粒子で、中に薬を封入して運ぶ、小さなカプセルのような構造です。
例えば、がん細胞に届きやすくなるように工夫したナノ粒子に抗がん剤を含有させることで、必要な場所に届けることができます。実際に臨床で使用されている「ドキシル」は、抗がん剤であるドキソルビシンをナノ粒子に封入することで抗がん剤の全身への作用を抑え、がん細胞に集まりやすくなります。このようにピンポイントで標的に届くようになれば、投与量を減らしたり、副作用を軽減したりすることができ、そのうえ治療効果を上げることもできます。そのための、疾患や治療目的に合わせて薬を届けるためのナノ粒子開発に取り組んできました。
 ―ナノ粒子は人工物ということですか?
―ナノ粒子は人工物ということですか?
そうです。現在使われているナノ粒子は、複数の材料を合わせて人工的に作製した粒子なんです。
人工の良い点は使う材料や構造をすべて自分たちで決められるので、品質管理や安全性評価がとても行いやすい点にあります。薬局で購入した薬にも成分表示がされているので、それを思い出してみてください。
表示にはどの成分がどれだけ入っているか細かく書かれていますが、人工的に合成された材料だからこそ、こうした管理がしやすいんです。ただ、人工的にさまざまな成分を組み合わせてナノ粒子をつくり、薬物を効率よく封入し、その封入した薬物量を測定して、など製造工程が複雑で高コストになってしまいます。
一方で、生物が作っている天然由来のナノ粒子が存在し、新しい治療薬候補として注目されています。
私が大学院生くらいの頃、人の体内、例えば尿や血液中に生体が分泌している天然のナノ粒子が存在しているという報告があり、話題になりました。これはあらゆる細胞が分泌している小さな膜小胞のことで、学術的には「細胞外小胞」が正しい総称になります。
人工の粒子研究をしていましたが、生体由来のナノ粒子にも強く惹かれました。
そんなときに、たまたま植物の研究をされている研究者とお話する機会があったときに、「植物細胞からも同じような小胞が分泌されているよ」と教えていただいたんです。
植物って、実は多様なタイプの小胞を出していて、その仕組みもまだ分かっていないことが多い。これは面白い!と興味が湧いて、これをきっかけに、生体由来の細胞外小胞に比べてまだ研究が進められていなかった、植物由来の小胞の研究に取り組み始めました。
 ―まず何から始めたんですか?
―まず何から始めたんですか?
まずは柑橘類、グレープフルーツなどから研究を始めました。
人工ナノ粒子で設計してきたような機能が、もし天然の小胞にも備わっているなら、そのままナノ粒子製剤として活用できるのではないかと考えていたんです。
この当時は、柑橘系の果物や野菜などの食用植物に由来するナノ粒子の報告がほとんどでしたので、私も試したところ、確かにナノ粒子がとれることが分かりました。
薬学で研究をしていることもあり、まだ当時はあまりナノ粒子の研究が進められていなかった薬用植物であるハーブや生薬に着目しました。
薬用植物も葉だけでなく根や種子などもあり、色々と試す中で、思ったよりも粒子が得られなかったりして・・・ハーブや生薬20種類以上の薬用植物の検討を進めていきました。その中で、他にも何か面白い植物はないかなと探していたところ、ちょうど植物由来の小胞についての共同研究を始めていたフィリピンの研究者から「モリンガはどうかな?」と紹介されたんです。
最初は「何それ??」という感じで、名前も聞いたことがなかったんです。
でも、色々と調べてみると栄養価も高く抗酸化作用も高いスーパーフードとして注目されている植物で、ナノ粒子としての機能も気になり始めました。
粒子の採取は植物の部位によって、もしくは生なのか乾燥なのかによっても量や質が全然違うので、とにかく試料が欲しくなってしまって・・・
どうしたら良いか悩んでいたら、たまたま行った展示会でARINGA MORINGAのブースにを見つけました。思わず飛び込みで「葉っぱ欲しいんです!」とお願いしてしまいました(笑)。
(後編に続く・・・)
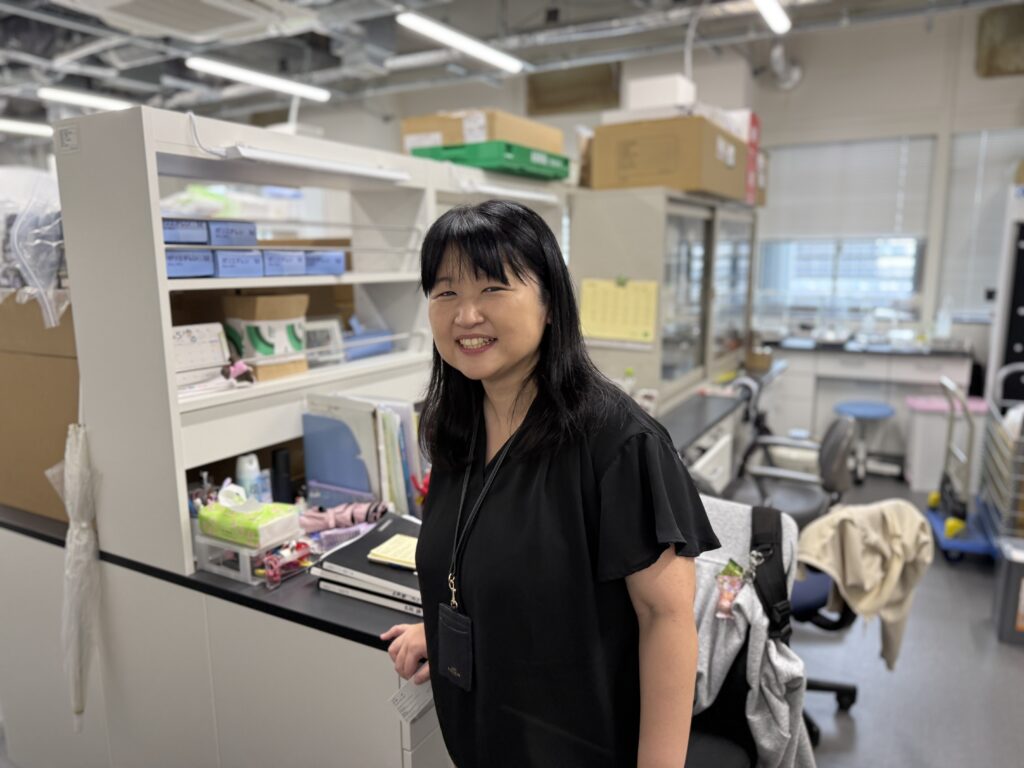
東京理科大学薬学部薬学科 助教
板倉 祥子(いたくら・しょうこ)
京都薬科大学にて薬学を専攻。その後、製薬メーカーや大学の研究所にて研究員として従事するほか、日本学術振興会特別研究の実績を経て、2023年より東京理科大学にて現職。日本薬学会や日本薬剤学会など各学会に所属のほか、日本ハーブ療法研究会において世話人も務めている。